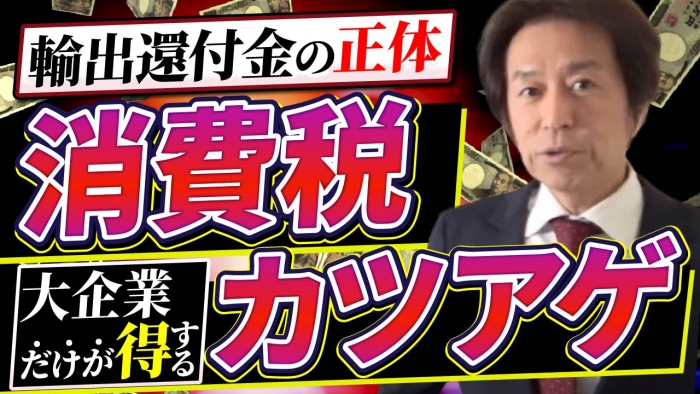今月のひとこと 2025年 9月1日
ChatGPT-5
最近はチャットGPTにはまっています。無料プランで使っていたのですが、ある日突然GPT 5に切り替わってしまって、私はあまり変化がないと思いましたが、世の中では前のGPT 4の方が良かったということで、非難轟々となってしまって、しかしアルトマンはあっという間に切り替えてしまいました。この素早さにも感嘆しました。
無料ではないのですが有料プランの一部に前のGPT 4が使えるようになっています。なぜこうなったかというと、GPT 4の方がわりと迎合的というかベンチャラを言うとか、良く言えば人に優しい点があって、GPT 4にメンタルな相談をしていた人が多くて、そういう人たちがGPT 5になって事務的になってしまい、違和感が出て非難轟々となったようです。普通の事務作業に使ってる場合は、あっさりしていて良いとは思いますが、メンタルな相談をしている人にとっては非常に冷たくなってしまったという感じがするらしいです。
これでAIも単なるコンピューターサイエンスの分野でなくて、心理学の分野にも影響を及ぼし、さらにはAIを外部から観察するという自然科学の分野にもなってきたようです。元になったニューラルネットはノーベル賞になりましたが、本来は数学であるコンピュータサイエンス分野はノーベル賞の対象ではなかったのですが、詳細は忘れましたが、タンパク質の分析とか、無理に自然科学に結びつけた印象があります。しかしこれからはブラックボックスであるAIは自然科学の対象になっていくのではないかと思っています。そのような論文も出来始めました。
普通の検索の延長線上であれば、あまり大したことはないというか、今のGoogle検索でもトップにAI検索の結果が出るようになっていますが、一番びっくりしたのは前回でも触れましたが、プログラムのコーディングが出来ることです。既にコンピュータ業界ではバイ(=ペア)コーディングと言って、日常的に使うツールになっているらしいです。
かなりややこしいコーディングもでき、これには非常に驚きました。これはすごいなと思っていたら人員整理の話がありました。日産は2万人、Microsoftも2万人の人員整理ですが、日産はご存じのように事業縮小、マイクロソフトは私の見るところエントリーレベルのプログラマーが整理されるのではないかと思っています。コーディングは全て一瞬でできてしまうので、そういうエントリーレベルのプログラマーは不要になると思います。
一方、出来たコードをチェックする人が要るので、ある程度のレベルがないとだめだと思います。だから全くの素人では作れないのですが、ある程度の知識があれば使えるというところです。いずれにしても少なくともコーディングの生産性は飛躍的に上がったようです。
コーディングが全く不得意の私には神の存在です。他のことはだいたいできるのですが、このコーディングだけはダメです。学生の頃IBMの適性検査を受けたのですが全然適性がなかった。自分でもそう思う。私が人生全体で書いたコードは数千行ぐらいしかないと思います。以前から自分でプログラムのコードが書ければどんなに嬉しいかとずっと思っていたので、今までやりたくてもできなかったことをどんどんやっています。
全ての仕様をプロンプトに入れるわけにはいかないので、とりあえず作ってあとは修正・修正でやっていくのですが、これがやってみないとわからないところがあるので何回もやり直して結構時間はかかります。相手が人間だと嫌になると思うのですが、機械だと思うといくらでも繰り返し聞けるし、恥ずかしいような初歩的な質問も気兼ねなくできます。最終的にはかなり複雑なプログラムができます。
私はPythonは全く知らず、使い方すら知らなかったのが、プログラムがどんどん作れるようになりました。エクセルのマクロもずっと敬遠してたのですが、これも複雑なマクロも作れるようになり、AIにはまってる最中です。ただAIはすぐにコードを吐きたがる。エクセルのフォーミュラで簡単に書けるものまでマクロにしようとする。ここはプロンプトで指示を与えないといけないところです。
消費税の本質と問題点
消費税はたった10%ですが、されど10%。最近は消費税の本質的な認識がだんだん浸透してきて、消費税は非常に経済の足を引っ張るという認識が広がってきました。消費者が払うということで消費税という名前がついているのですが、これ全くの嘘で実際は事業者が払います。10%から控除額を引いた残りを支払うということで、事業者全体で10%の第二法人税が課されています。法人税であろうが第二法人税であろうが、最後は消費者に転嫁されてしまうわけで、特に消費税を消費者が直接負担するわけでもありません。
本来の法人税では赤字なら払わなくて良いですが、売り上げに対してかかる消費税は必ず支払わないといけません。従って、一番未納が多い税目が消費税です。これが日本経済の足をじわじわ引っ張っているのです。
消費税は輸出企業には還付があります。これの統計金額が公表されてないというのもおかしな話ですが、約30兆円ぐらいの消費税収入全体のうち約9兆円が還付になってるらしい。だから消費税について、よく言われている
「あなたたち消費者が消費税10%を負担しているのです。10%は預かり金として事業者が受け取り、事業者がまとめて支払っています。その消費税は社会福祉に使われております」
というのは全くの嘘であるということがよく分かると思います。なんと我々が負担しているとされている消費税の1/3は輸出補助金に化けているのです。また、実際に消費税を負担してるのは中小企業などの事業者です。消費者が消費税分として10%を払っているのは単なる便乗値上げで、徴収する必要はありません、任意です。
ちなみに現時点では国民負担率、つまり雇い主と折半して払った社会保険料と所得税で48%になっているとのこと。さらに使うときには、最終的に10%を消費税として負担しなくてはならないので、他の自動車税とかガソリン税とかを除いても、負担は60%近くにもなります。四公六民どころか、六公四民になっているのです。
トランプ相互関税と消費税
トランプの相互関税には、日本ではあまり報道しませんが、この10%が含まれています。アメリカは勝手な国なので、消費税はなくて売上税しかありませんので、還付はありません。ここで不公平が起きているのですが、日本の報道ではほとんど触れられていません。関税騒動の初期のころにトランプが消費税をやり玉に上げたときは、少し報道していましたが、その後は触れられなくなりました。
こう言うと、仕入先がすでに負担してるので特に得ではないのではないか、還付されるのは当然ではないかという話がありますが、消費税というのは要するに値上げですので、それを販売価格に転嫁しようがしまいが勝手なわけで、要するに販売金額の問題です。だから消費税が10%に上がった時に「消費税分をアップします」というのは単なる値上げであったということです。また他の国内の非輸出企業と不公平になります。
トランプが消費税が実質の輸出補助金であるということで、相互関税のベースに使っているというのもあって、だんだん認識が深まってきました。それで最近は消費税減税みたいな話がいろいろ増えてきてるわけです。
付加価値税の発明
欧州では正直に付加価値税(VAT)と言うわけで、要するに付加価値にかかってきて、その大半は人件費です。結局、人件費を抑える方向に作用して、賃金が上がらない要因の一つにもなっていると思います。通常の法人税とこの第二法人税と言われる消費税が違うのは賃金を含めるか含めないか、赤字になったら本来の法人税は支払わなくて良いのですが、消費税は支払わないといけないことになります。
このままほおっておいて税率が15%とか20%になると本当に国がもたなくなると思います。こういうとヨーロッパでは25%が普通だという話ですが、軽減税率がたくさんあって、基本的に日本で言うと昔の物品税に相当するような感じで、普通の通常の日用品はほとんど税金がかからないようになっているとのこと。こうなるとまた国内的には還付の問題が出てきてややこしくなります。
以前に触れたと思いますが、もともと付加価値税とか消費税とかいうのがフランスで発明された時は、輸出補助金を払っていたがガット(GATT)の規制で輸出補助金を出せなくなったので、その代わりにこの付加価値税というのが発明されたということで、非常に頭の良い人が考えたと思います。それに悪乗りして、消費税という名前をつけて一般国民が負担するんだ、という印象付けをしたのは当時の大蔵省だったと思います。
今後増税があったとしたら、結局一番被害を受けるのは中小企業だと思います。一般国民もそれなりに増税になるわけですけど、得をするのは大企業、特に輸出企業は還付があるのでウェルカムだと思います。
先日の読売新聞の「地球を読む」欄の吉川 洋氏の記事が面白かった。
約40年前、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」などとおだてられ、バブルに踊った日本経済は、1990年代に急降下した。国力の目安となる1人当たり名目国内総生産(GDP)は、2000年にはルクセンブルクに次ぐ世界2位だったが、その後は坂を転がり落ちるように下がり、24年には38位となった。1人当たりなので、人口減とは関わりのない低迷である。
「急落の原因はデフレだった」と言う経済学者やエコノミストは多い。実際、「デフレ脱却」は政府の掲げる金看板であり、日本銀行が13年から10年以上続けた「異次元」の金融緩和政策は、デフレ退治を目指して行われた。しかし、長期停滞の真因はデフレではない。
と始まり、主な原因は日本企業の技術革新の不足だったという分析です。これはまさにその通りで、本当に日本企業は何もしなかったし、経団連も何も言わなかった。ひたすら賃金を上げずに派遣に頼り、コストカットに走って何もしなかった。失われた30年の主原因であると私も思います。
1980年代後半から1990年代のバブル崩壊までは本当にいろんなことをやったような気がします。失敗も当然ものすごく多かったですが、ジタバタしてたような気がします。
今で言うと規模はだいぶ大きいですがソフトバンクの孫さんが、そのような感じがします。すごいお金をあちこちにぶち込んでるみたいですが、やはり向う見ずにジタバタしないと新しいことはできないと思います。ほとんどの企業は何もせずに、じっとしているだけでデフレですから、利益は出たということでしょう。結局発展し損ねて世界での順位がダダ落ちになったということです。
しかしこの吉川氏のコラムの最後には、人生で使い残した金融資産に相続税に加えて新税を課税する、なんと結果的に増税ではないかという話で後半はずっこけてしまいましたが、もし前半の技術革新で、これから頑張って日本が伸びればこういうつまらん増税みたいなことしなくて良いのではないかと思います。要するに吉川氏はもう日本は伸びない、増税しかないと思っているのでしょう。
今月の読み物は「リボルバー」 単行本 2021/5/26 原田 マハ 著 文庫 ¥858
展示会が開かれているゴッホに興味のある方に最適。全体的にミステリー・フィクションですが、ゴッホや弟のテオとの関係とか、面白い逸話が多いです。以下はGPTがつくりました。
原田マハさんの小説『リボルバー』は、フィンセント・ファン・ゴッホの死をめぐる謎に光を当てる、美術ミステリーの傑作です。本作は、オルセー美術館の女性学芸員が偶然手にした一丁の古い拳銃から物語が始まります。その銃こそ、ゴッホが命を絶ったとされるものであり、彼の死の真相をめぐる鍵となる存在です。物語は、この銃を通して浮かび上がるゴッホの最期の姿、そして彼を取り巻いた人々の想いを丁寧に描き出していきます。実在の画家や歴史的事実を巧みに織り込みながら、フィクションとしてのスリリングな展開を見せる点が、本作の大きな魅力となっています。
原田マハさんは、これまでも『楽園のカンヴァス』や『ジヴェルニーの食卓』など、美術と文学を融合させた作品を数多く発表してきましたが、『リボルバー』はその集大成ともいえる力作です。ゴッホの芸術への情熱、孤独、そして彼の生涯を通して表現し続けた「生きることの意味」が、物語全体を深く貫いています。美術館を歩いているような臨場感ある描写や、作品に対する細やかな解説も盛り込まれており、美術に詳しくない読者でも自然に引き込まれる構成になっています。
また、ゴッホの死は「自ら命を絶った」とされるのが通説ですが、本作では異なる可能性に迫ることで、新しい視点から芸術家の人生を再考させてくれます。単なる推理小説ではなく、人間存在そのものや芸術の力を問いかける文学的要素が強く、読後には深い余韻とともに、多くのことを考えさせられます。原田マハさん独自の温かみと美術への愛情が随所に溢れており、読む者の心を優しく包み込みながらも強烈な印象を残します。
『リボルバー』は、美術小説としての知的な楽しみと、ミステリーとしての緊張感を併せ持つ作品です。ゴッホの絵画や人生に興味のある方はもちろん、芸術を通じて人間の本質に迫る物語を求める方にぜひおすすめしたい一冊です。読後には、ゴッホの作品を改めて見直し、その背後にある人間の苦悩や情熱をより身近に感じられることでしょう。