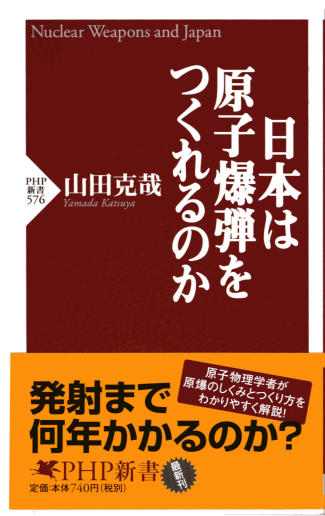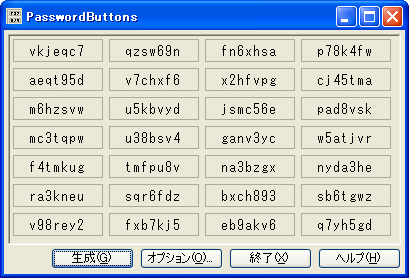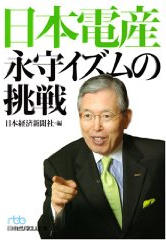絵や写真をクリックすると、そのページに行けます
6月1日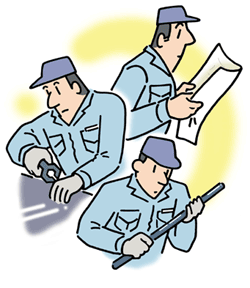 やっと在庫調整にも目処
やっと在庫調整にも目処が付き、少しはほっとした感じがありますが、雇用統計では求人倍率が最低を示したとのことで、雇用関連は少し景気より遅れますので、まあこんなもんかと言うところでしょう。 しかし、これから本当に上がっていくのか? と言うと上がってもダラダラではないでしょうか。 また、嵐の後は元通りには普及しないのではないでしょう。
アメリカのGMがチャプター11を6月1日にでも申請するのではと報道されています。 さっさとやれば良いのにと思うのですが、いろいろ交渉プロセスがあるみたいで、やっと申請に漕ぎ着けるようです。 日本の会社更生法と違って再生を目的にしますので、経営は非常にやりやすくなると思います。 アメリカの大手の航空会社はほとんどが申請の経験があり、その間にも飛行機がストップしたという話は聞いた事がありません。 日本では悲観的な論調が多いですが、中期的にはGood News だと思います。
先週のサンプロ番組の加藤・竹中論争は面白かったですね。 加藤さんの言っている事はヨーロッパの社民と同じで、何でこんな人が自民党に居れるのか不思議です。 まあ片や民主党も旧社会党を含んでいますので、日本の政治はどこもかしこもファジーなんですね。 竹中さんはいつもながら明快で、市場原理主義と言われて反論。 あれだけ言われて銀行に介入したのがどこが市場原理主義なんだ。 本当の保守のブッシュが、市場介入に非常に後ろ向きだったのが印象に残っていますが、これが本当の保守なんでしょうね。

自己責任主義、市場優先、小さな政府などなど。 それに比べると日本はどこかファジーで、竹中さんの方が余程保守本流みたいに見えます。 それにしても税収を上回る国債を発行して、元々危うい財政がますます怪しくなります。 もっとも、国の財政を家庭の借金と類似させるのは、財務省の手なのか、間違った想定を植えつけます。 むしろその家の主人が奥さんに多額のお金を借りているようなもので、その家トータルでは特に借金はないのです。 住宅ローンと類似させるのは何か意図を感じますね。
行き詰った最後は国家的な徳政令つまり借金(国債)棒引きです。 国債が文字通りタダの紙切れに。 もっと簡単なのは、預金封鎖。 個人金融資産が1500兆円もあるので、これを一気にチャラにしたら解決。 幸いアメリカと違って日本国債の海外保有率は極めて少ないのです。 よかった・・ だけど自分の預金が・・ だからタンス預金なんですね。 しかしこれも新円を発行して、旧円を無効にしたらおしまいです。 いずれにしても、現物のキャッシュは全体から見たらわずかなもので、本格的には日本以外の銀行口座に追跡できないように送金しておくのが良いでしょうが、合法的には不可能です。
これから何が起きるのかと言うと、これまでは必ずインフレになると思っていて、アメリカの経済学者でもそういう人がいますが、日本の経験ではそうならなかったですね。 世界的に少し金余りになりましたが、起こった事は、アメリカの住宅バブル、原油のバブル、資源のバブルが起こったのでした。 みんなの頭の中にあるインフレと言うのはこれからしばらくは起こらないのでしょう。 現在世界的に金余りが加速していますので、これから何が起きるのか良く良く見ておきましょう。

もしインフレになったら、財政は安泰です。 名目の税収が増えて、国債の価格が下落します。 政府は喜び国債を持っている人は価格が下落しますし、満期で償還しても、貨幣価値は下がっているでしょう。 まあだけど、ましなシナリオです。 これだけお金をジャブジャブ出してインフレになったらどうするんだ! と言う人がいますが、どこが悪いの? とみんな思っているんです。
最悪はデフレが進行することです。 過去の例でもひどいのは良く分かったと思いますが、有効な治療法がない、名目の税収が減る、 しかし利払いは必要で、利払いが税収を上回ると国家のデフォルトになります。 1000兆になったとして(数年でなってしまう)、その3%は30兆円です。 税収のあらか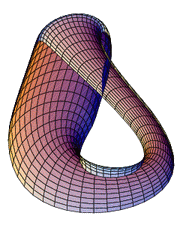 たが利払いで消えることになります。 従って最後は消費税です。 いずれにしても税であろうと保険金であろうと誰かが負担しないといけないのです。
たが利払いで消えることになります。 従って最後は消費税です。 いずれにしても税であろうと保険金であろうと誰かが負担しないといけないのです。
今回は少し余裕が出たので、延々と少し将来のことを考えた事をかいてみました。 ITの分野では、最近懐かしい名前を見ました。 マセマティカのウルフラムです。 何でもGoogleの先を行く質問形式の検索エンジンを開発したとの事。 英語版がリリースされているとの事ですが、なかなか答えてくれないとのこと。
マセマティカは、数式を可視化するソフトで、例えばややこしい理論物理の数式をビジュアル化して見せるというような事に使われています。 一番最初にワークステーションを作ったときは、これを動かすのが目的でしたが、実現せずに終わってしまって、現在は通常のPCで動作します。 これのセールスとやっていた人と確か会ったこともありました。 Googleのときも、検索エンジンはこれで終わりか、と思っていましたので、やられた! と思いました。
それにしても、Google は全世界の知識をDB化すると言うすごい目標を持っています。 これは私が思うには、宗教的な背景が大きいと思います。 やはり全知全能の神が存在、偏在かもしれませんが、すると言うのは、ものを考える上で物凄い制約と言うか、規範になります。 誰か知らんがそんなものがあるのなら、それに近づいてみようと思う要になるでしょう。 湯川秀樹や日本の物理学者が3と言う数字に違和感があったので、クオークに乗り損ねたんですね。 湯川博士の中間子は、そのせいではないですが、クオークが2つでした。 運命的ですね。 益川さんの先生の、ノーベル賞をとり損ねて死去してしまった名古屋大学の坂田昌三博士は、八道説でしたから。
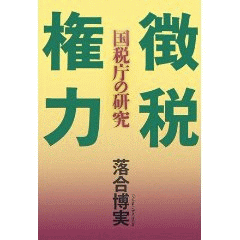 今月の読み物は、徴税権力―国税庁の研究 (文春文庫) 落合 博実 著¥550 です。 あまり期待せずに読み出したのですが、まあ良くここまで書いたと思いました。 あとがき代わりの立花隆との対談がなければ、フィクションかと思いました。 流石に情報提供者は既に鬼界に入っておられる様で、そうでなければ大変な事です。 政治家の介入、金丸信から、そんなイメージが無い小泉元首相まで、大企業、マスコミへの対応。 最後は創価学会との関連。
今月の読み物は、徴税権力―国税庁の研究 (文春文庫) 落合 博実 著¥550 です。 あまり期待せずに読み出したのですが、まあ良くここまで書いたと思いました。 あとがき代わりの立花隆との対談がなければ、フィクションかと思いました。 流石に情報提供者は既に鬼界に入っておられる様で、そうでなければ大変な事です。 政治家の介入、金丸信から、そんなイメージが無い小泉元首相まで、大企業、マスコミへの対応。 最後は創価学会との関連。
国税庁とは何か。元朝日新聞記者として長年同庁を担当し数々のスクープをものにして名を馳せた著者が、徴税機関が有する「巨額マネーを巡る情報収集力」という視点から、その強みや問題点を解き明かしていく。同庁については「秘密主義の官庁の中でもガードの堅さは群を抜いている」と指摘しながらも、内部の協力者から得た極秘扱いの「内部文書」を紹介するなどして、脱税事件の舞台裏にも迫る。
同庁の情報収集力と資料分析力は、「最強の捜査陣」と喧伝される検察庁をもしのぐと著者は言う。例えば1993年に起きた「金丸事件」。自由民主党元副総裁・金丸信氏の巨額脱税を摘発した同庁査察官の手腕を振り返る。
その一方で「与党と一体となって行政を進める大蔵省(現財務省)の外局にすぎない国税庁は、有力政治家からの圧力に弱い。(本件の成果は)やはり例外中の例外であった」とも論じる。「永田町からの圧力」により、脱税事件が単なる申告漏れとして処理された事例も少なくないと言い、事件としての立件に執念を燃やす地検特捜部との間に確執が生じることもあったと指摘する。例えば、91年の地産グループ総帥による43億円の申告漏れなど、政治家が同庁の調査に介入したケースを関係者の実名を挙げて告発する。
(日経ビジネス 2007/03/26 Copyrightc2001 日経BP企画..All rights reserved.)
内容(「BOOK」データベースより)
五万人を超す組織が日々絶え間なく、個人や企業の経済取引や資産形成など金の動きに眼を光らせている。そこには膨大な「マネー情報」が集積されていた。国税庁はその比類ない機能により独特の凄みと嫌らしさを兼ね備えた組織だった。極秘資料を満載!スクープ記者30年の取材成果がここに―。
内容(「BOOK」データベースより)
膨大な「マネー情報」が集積される国税庁。その内情に相当程度に踏み込めたのは、長年の取材活動で当局の「内部文書」を入手できたことが大きい。漏洩すれば国家公務員法に問われかねない危険な極秘資料を、敢えて提供してくれた国税庁や国税局の幹部と職員。スクープ記者30年の取材成果がここに結実する。
立場上財務省の一外局にすぎず、世の関心もけっして高くはない国税庁。だが、その素顔は、警察・検察にまさるとも劣らぬ巨大な情報収集力を秘め、あらゆる国民のうえに君臨する一大権力機構である。本書は朝日新聞記者時代、国税庁担当として幾多のスクープを飛ばしてきた著者が、秘蔵資料を縦横に駆使し、“税の総本山”の全貌をはじめて白日のもとにさらす、全納税者必読の書。政治家、大企業、新興宗教、マスコミとマルサたちの知られざる暗闘をスリリングに描き出している。(UH)
 市場はダラダラ相場が続いています。 在庫調整はともかく、流石に雇用、設備投資は時間がかかります。 順調に行っても、恐らく来年の後半までかかると思います。 それにしても中国は元気です。 運も良くて、来年の上海万博まで持たせれば、その後は波に乗れるのではないでしょうか。
市場はダラダラ相場が続いています。 在庫調整はともかく、流石に雇用、設備投資は時間がかかります。 順調に行っても、恐らく来年の後半までかかると思います。 それにしても中国は元気です。 運も良くて、来年の上海万博まで持たせれば、その後は波に乗れるのではないでしょうか。



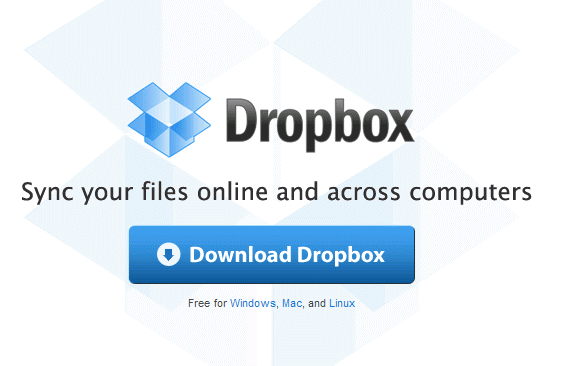


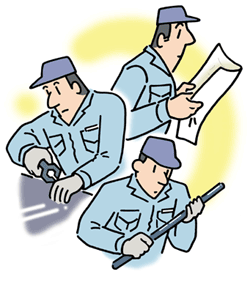
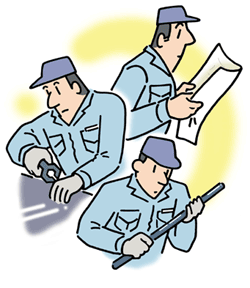


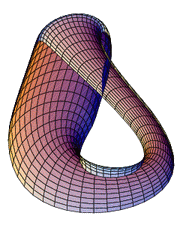
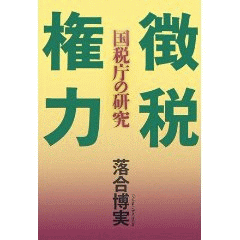





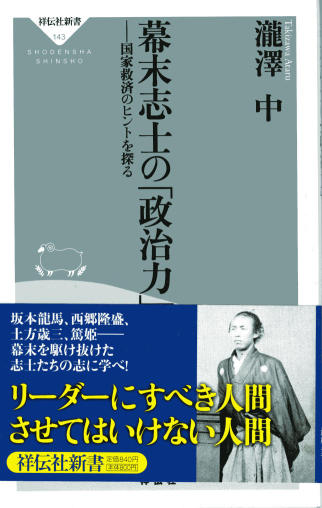



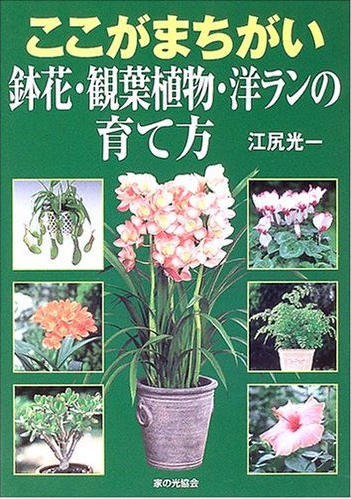 ここがまちがい 鉢花・観葉植物・洋ランの育て方
ここがまちがい 鉢花・観葉植物・洋ランの育て方